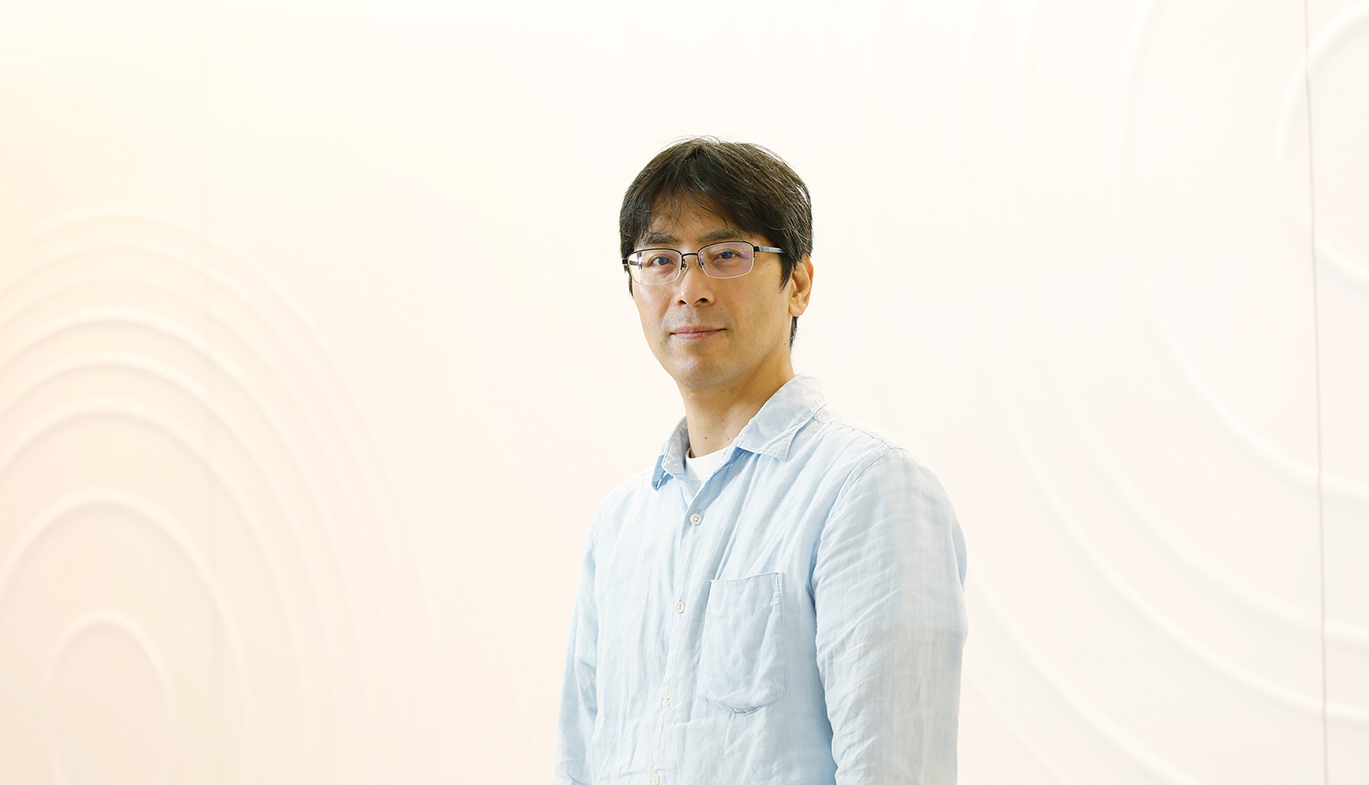責任のあるポジションを任され、忙しい毎日を過ごしていた小林さん。びまん性大細胞型B細胞リンパ腫がわかったきっかけとなったのは、会社の健康診断でした。乳房に左右差があり、さらにマンモグラフィ検査で病気の判断がつきにくい高濃度乳腺だとわかり「念のため、乳腺外科で検査を」と勧められたそうです。すぐに専門医のいるクリニックの予約を取りましたが、2~3週間後には自分でも乳房の左右差がはっきりとわかるようになっていたそうです。クリニックではエコーとマンモグラフィ、内診が行われ、良性の肉腫または炎症性の乳がん、悪性リンパ腫のいずれかという診断がくだり、すぐに大学病院へ行くようにと紹介状を渡されました。会社の健康診断から、わずか1ヶ月後のことでした。
「大学病院へ行くまでの数日間、自分でもインターネットでそれぞれの病気を検索してみました。良性のものであれば問題はありませんが、炎症性乳がんは難しい病気だと知り、悪性リンパ腫に至っては種類がありすぎて調べきれませんでした」。
大学病院でも改めてマンモグラフィが行われ、その後、生検とMRI検査を経て、2週間後にはびまん性大細胞型B細胞リンパ腫の確定診断が出ました。
「乳腺外科で確定診断を聞いてから、わずか2日後には同じ大学病院の血液内科の初診を受けることができました。その日に細胞診、翌日には院内でPET検査があり、さらに次の日は金曜日だったにも関わらず主治医の先生から電話をいただき、土曜日からの入院を勧められました。検査にしても、入院にしても、かなり急な調整をしていただいたようです。でも、どうしても会社で引継ぎが必要だったため、その電話でできる限りの話を伺い、月曜日からの入院にさせてもらいました。その時は、一日でそんなに変わるものなのかなと呑気に考えていたのです」。
確定診断直後は、ショックや悲しみなどを感じることはほとんどなかったという小林さん。もちろん平常心だった訳ではなく、「感情がブロックされたような感覚」だったそうです。
「不謹慎だとは思いますが、入院直後に、これで少し仕事を休んでゆっくりできるなと考えていました。ただ、治療が大変なのはわかっていたので、復職しても同じポジションで同じように仕事をすることは難しいだろうと理解していました」。